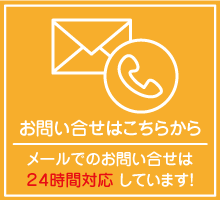日本で外国法事務を取り扱いたい外国の弁護士資格を持っている外国人の方々へ、外国法弁護士法人の設立ができるようになったので、ご説明していきたいと思います。
平成28年3月1日に外国人弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)が施行されました。
ポイントは、今まで外国法弁護士のみの法人は設立することができませんでしたが、改正により設立することが可能になったことです。詳しくは法務省発表のHPをご覧ください。
業務範囲は外国法に関する法律事務です。弁護士法72条に関わる事務はできません。もちろん他の、資格を有する者のみが行うことができる法律系の独占業務もすることができません。
外国法弁護士法人を設立するには、所属弁護士が外国法弁護士に承認されていなければいけません。承認・指定申請手続きは以下になります。
法律要件:3年以上の職務経験(日本の法律事務所での労務提供期間も考慮されます)
必要書類
- 承認申請書(写真及び収入印紙(27,500円分)貼付)
- 申述書
- 履歴書
- 旅券又はその他の身分を証する書類の写し
- 外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
- 外国弁護士としての職務経験を証する書類
(勤務証明書など) - 住居を確保していることを明らかにする書類
賃貸借契約書の写し - 損害賠償能力を有することを証する書類
申請者を被保険者とする弁護士賠償保険加入証書の写し - 申請・宣誓時に朗読し署名する書類
弁護士法7条各号に掲げる者でないこと誓約する書面
外弁法10条1項2号イから二までに掲げる者でないことを誓約する書面
誠実に職務を遂行することを誓約する書面 - 適正かつ確実に職務を遂行するための計画を証する書類
被雇用者の場合 雇用契約書の写し 所属弁護士事務所の業務内容等事業概要を記載した書面
所属弁護士事務所の賃貸借契約書の写し
雇用主作成の上申書
(監査法人からの所属事務所の財務状況を評価する書類)
単独開業の場合 開設する事務所の賃貸借契約書の写し 開業する事業の契約書
- 財産的基礎を有することを証する書類
被雇用者の場合 所属事務所が雇用期間中、被雇用者の日本での滞在に関して支援することの保証書 所属事務所に関する監査法人からの同事務所を評価する書簡
単独開業の場合 自身の預金残高証明書
外国法事務弁護士法人制度の概要
社員の資格
外国法事務弁護士のみが社員となる(第50条の4)
業務範囲等
- 外国法に関する法律事務を行う
(第50条の5)
※ 法人の設立により外国法事務弁護士が取り扱うことができる業務が拡大するわけではありません。 - 弁護士を雇用する場合等において、弁護士に対する不当関与を禁止している
(第50条の11、第50条の12)
事務所
複数の事務所を設けることができる(第50条の13により準用される弁護士法第30条の17本文)
監督
弁護士会及び日本弁護連合会の監督を受ける(第21条により準用される弁護士法第31条第1項及び第45条第2項)
法人の設立手続き
外国法事務弁護士法人の設立手続につきましては,弁護士法人の設立手続に準じており
- 定款の作成及び認証
- 主たる事務所の所在地にある法務局への設立登記の申請
- 弁護士会への成立の届出
などが必要となります。(法務省HPより)
まとめ
法律改正前は外国法事務弁護士のみの弁護士法人は設立できませんでしたが、平成28年3月より可能になりました。
外国法事務弁護士事務所の設立をお考えの方がいましたら、行政書士は官公署に提出する手続きの代行ができますので、お気軽にお問合せいただければ幸いです。